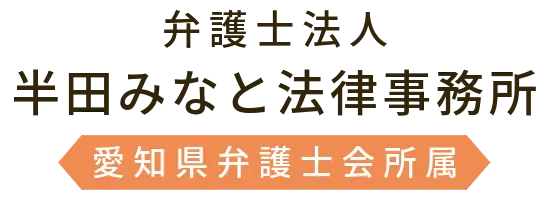認知症の方が相続関係者にいると、遺産分割協議を行えないため相続手続きが進まない事態になってしまう可能性があります。遺産分割協議をせずに法定相続分どおりの遺産分割をする方法もありますが、相続税が高額になってしまうなど、問題点も多い方法となってしまいます。成年後見制度を利用することによって遺産分割協議をすることができるものの、さまざまな注意点があることを抑えておかなければなりません。
今回は、認知症の方が相続人である場合の問題点や注意点を解説し、対処法をご紹介します。また、被相続人が認知症であった場合の対処法や、相続関係者に認知症の方がいてもトラブルを防ぐ方法なども解説しています。ぜひ参考にしていただき、必要に応じて弁護士など専門家のサポートも受けて、スムーズに相続手続きを進めていただければと思います。
認知症の相続人がいると遺産分割協議はできない!対処法は?
効力のある遺言書がない場合、遺産分割協議によって被相続人の預貯金や不動産などの財産を誰が相続するのかを決定します。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、相続人の中に認知症の方がいる場合には、判断能力や意思能力が低下していると見なされ、遺産分割協議ができない可能性があります。その場合は、代筆で署名するなどして無理に遺産分割協議書を作成しても無効となります。
遺産分割協議をしないままにしておくと、相続した貯金を引き出したり不動産を売却したりできないだけでなく、相続税額の負担が大きくなってしまう可能性もあります。相続税の申告には期限があり、被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に申告する必要があります。遺産分割協議ができず相続財産の取得人が決まらないままこの期限が迫ると、「未分割」の状態で申告しなければならなくなります。「未分割」だと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額控除といった相続税額を軽減するための特例が適用できなくなるなど、本来受けられるはずのメリットがなくなってしまうのです。
遺産分割協議ができない場合でも相続手続きを進めるための対処法としては、以下の2つが考えられます。
- 民法で定められた遺産分割の目安となる割合である「法定相続分」で相続をする
- 認知症の相続人に「成年後見人」を付けた上で遺産分割協議を行う
しかし、どちらの方法にも問題点や注意点があるため、メリットとデメリットを比較した上で検討しましょう。詳しく解説していきます。
法定相続分で遺産分割をする際の問題点
「法定相続分」で遺産分割をする場合には、すべての遺産が他の相続人との共有状態となります。共有状態にある財産に変更を加えるには共有者全員の同意が必要となり、それによってさまざまな問題が発生します。共有状態の不動産と預貯金について、それぞれどんな問題があるのか見ていきましょう。
不動産の活用や売却ができない
法定相続分で土地や建物などの不動産を相続すると、その不動産は相続人全員による共有状態となります。共有状態の不動産を増改築したり、賃貸や売却をしたりする際には、共有人全員の同意が必要です。特に、共有人の中に意思能力のない認知症の方がいる場合には、成年後見人を付けて同意を得ることが必要となります。
また、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続登記とは相続によって取得した不動産の名義変更手続きのことで、義務を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる可能性もあります。相続登記の手続きには遺産分割協議書の提出が必要ですので、相続人が認知症で遺産分割協議ができない状態のままだと義務違反となってしまいます。
相続登記の義務が導入された背景や、期限内に相続登記できない場合の対処法など、さらに詳しくは以下の記事もご覧ください。
「相続登記の義務化とは?期限や罰則、簡単に履行できる新設制度も解説」
預貯金の引き出しや名義変更ができない
共有相続人となった場合、それぞれの相続人は自身の持分に応じた金額について、被相続人の預金口座から引き出し(払い戻し)をすることができます。しかし、相続した預貯金を引き出す際に、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることが多いのが実際のところです。これは、その相続人に預金口座が相続された事実や、相続された割合について金融機関が把握し、トラブルを防ぐためです。
ただし、遺産分割協議書がない場合でも、「150万円」または「当該銀行にある預貯金額 × 1/3 × 法定相続分」のどちらか少ない金額までは払い戻しを受けることができます。これには葬儀費用などの相続人の負担を減らす目的があり、「預貯金の仮払い制度」と言われています。
成年後見人を付けて遺産分割協議をする際の注意点

相続人の中に認知症の方がいる場合に遺産分割協議をするには、成年後見制度を利用するのが最も一般的な方法です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となった方を、法律的に保護・支援するための制度です。後見人は家庭裁判所によって選任され、被後見人の財産管理やさまざまな契約手続きなどを代わりに行います。成年後見人が就任すれば、認知症の相続人に代わって後見人が遺産分割協議に参加することで協議を成立させることができます。相続放棄をする場合も、後見人によって手続きが可能となります。
しかし、成年後見制度を利用する際には注意しておくべき点もあります。1つずつ見ていきましょう。
後見人に報酬が発生する
成年後見人に就任するのは、親族や、家庭裁判所によって選任された弁護士や司法書士などの専門家です。専門家が後見人になった場合、後見人に報酬を支払う必要があります。報酬は月額2万円から6万円程度が目安で、財産額や事務内容などによって金額が異なります。
認知症の本人が亡くなるまで続く
原則として、認知症を患う本人が死亡するまで成年後見人が付いた状態が続きます。遺産分割協議の時だけ成年後見人を付けるといった利用はできないので注意しましょう。後見人への報酬も、本人が亡くなるまで支払いを続けることになります。
専門家が後見人に選ばれる可能性が高い
親族を成年後見人にすればいいと思う方もいるかもしれませんが、後見人の決定権は家庭裁判所にあり、誰が後見人に選ばれるかは申立てをしないと分かりません。現状では、専門家が選任される確率のほうが圧倒的に高くなっています。令和6年の実績を見ると、親族が選任されたケースは17.1%、親族以外が選任されたのは82.9%でした。(参考:成年後見関係事件の概況)
また、成年後見人の選任申立を行ってから就任するまでには1~3ヶ月程度かかるため、相続税の申告期限に間に合うように早めに行動しましょう。
他の相続人の希望が通るとは限らない
後見人には、被後見人の利益を最優先に行動する義務があります。そのため、遺産分割協議でも被後見人の不利益となる内容には原則として同意できません。
もしも本人の意思能力が十分であった場合、相続人全員の同意があれば「すでに十分な財産を持っているから子どもに多く遺産を分割する」という分割協議が可能です。しかし、後見人を付ける以上、このような本人にとって不利益となる内容を希望しても、後見人が認めるのは難しいと考えられます。認知症の相続人には法定相続分の財産を確保することになるなど、遺産分割内容が制限される可能性があることを覚えておきましょう。
また、後見人は被後見人が亡くなるまで本人の利益のために行動するため、生前贈与もできません。相続税対策に効果的な生前贈与ですが、これは本人の財産を譲渡する行為ですので、本人の利益にはならず、後見人が認める可能性は低いでしょう。さらに、家族であっても勝手に被後見人の財産を使うことができなくなります。
被相続人が認知症であった場合の対処法やトラブル防止法
<画像>

被相続人(亡くなった方)が認知症を患っていて意思能力が不十分であった場合には、作成した遺言書や生前贈与など、すべての法律行為が無効となってしまいます。遺言書が無効になると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。また、認知症になってから生命保険に加入したり、不動産を売却したりした場合にも、契約が無効となります。
遺言書の作成や生前贈与などをする場合には、認知症になる前に行うのがポイントです。公証役場で公正証書を作成したり、医師に意思能力があると証明する診断書をもらったりしておくことで、遺言書などの法的手続きが有効となる可能性が高くなります。
また、成年後見人が付いている方でも、一時的に意思能力が回復した場合には、2人以上の医師の立会いのもとで一定の様式に従って遺言をすることができます。
相続関係者に認知症の方がいてお困りの場合は弁護士にご相談を
認知症の相続人がいると遺産分割協議を行うことができません。遺産分割協議をせずに法的相続分で遺産分割をしても、不動産の増改築や売却のために相続人全員の同意が必要となり、預貯金の引き出しもできない事態になります。成年後見制度を利用することで遺産分割協議をすることができますが、後見人への報酬支払いや遺産分割内容の制限が発生するなど、注意点もあります。
相続関係者に認知症の方がいる場合は、早い段階から準備を整えておくことがトラブルを避けるために重要です。有効な遺言書の作成サポートや遺言執行、トラブル防止の観点からのアドバイスなど、法律的な目線でサポートを受けることができます。
半田みなと法律事務所は、半田市を中心に知多半島全域で相続問題についてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。弁護士とファイナンシャルプランナーが連携し、相続に関する法律や税務など、トータルサポートをご提供しております。少しでもお力になれればという思いで、初回30~60分の無料法律相談を実施しており、弁護士費用も比較的低価格でご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。