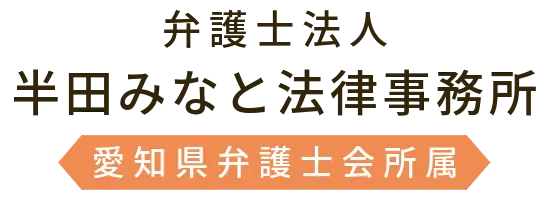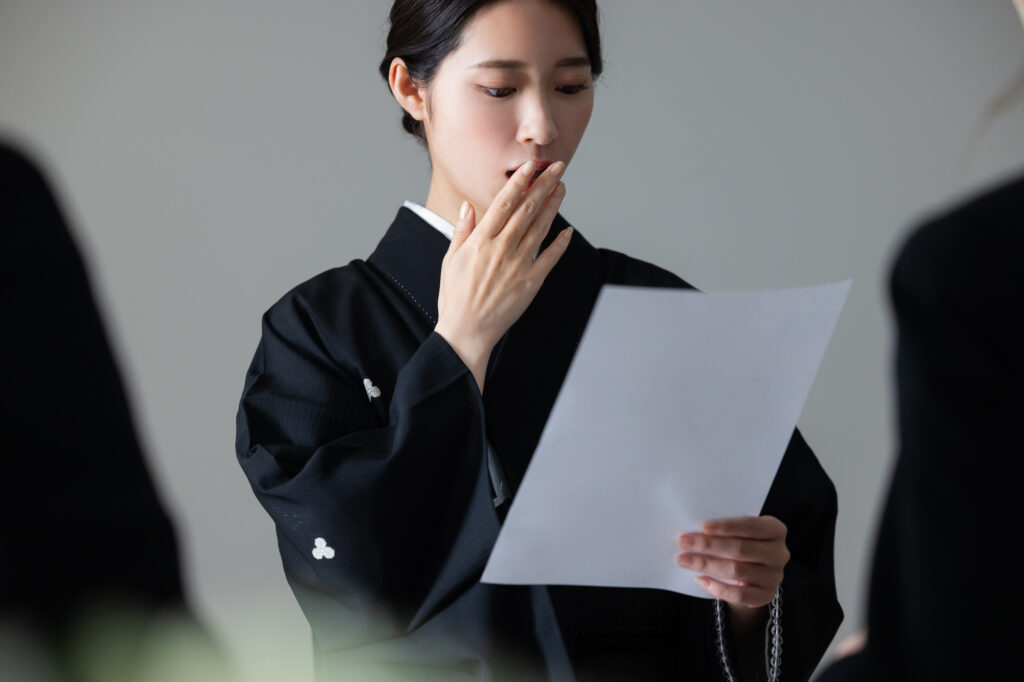
離れて暮らす親が亡くなった際、親と同居していた他の相続人が勝手に遺産を使ってしまっていたという事例は非常によく見られます。
亡くなった方(被相続人)の相続財産を使い込まれると、相続人の方が本来取得できるはずの遺産が減ってしまいます。使い込みが疑われる場合には相手に返還を求める方法がありますが、時効を迎える前に早急に対処する必要があります。
今回は相続財産の使い込みでよくある事例や、使い込まれた相続財産を取り戻せる事例・取り戻しができない事例についてご紹介します。使い込まれた財産を取り戻す手続きの流れや必要となる証拠資料などについても解説していますので、最適な解決を図るためにぜひ参考にしてください。
相続財産の使い込みとは?よくある事例
相続財産の使い込みとは、被相続人の生前に預貯金や不動産などの財産を管理していた人が、他の相続人に無断で相続財産を自分のために使用したり勝手に処分したりすることです。
よくある事例には以下のようなケースが挙げられます。
- 被相続人の預貯金が相続人の1人によって生前に無断で引き出され、使われていた
- 被相続人を介護していた人がお金の管理を任されており、横領された
- 被相続人が不動産を所有しており、相続人の1人が勝手に売却した
- 被相続人が不動産賃貸業を行っており、相続人の1人が無断で入ってきた賃料を使い込んだ
- 被相続人名義の株式を相続人の1人が勝手に売却し、売却金を自分名義の口座へ送金した
相続財産の種類や調査方法などについて詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。相続財産について
使い込まれた相続財産は取り戻せる?事例で解説!
相続財産の使い込みが発覚した場合、取り戻せる事例と取り戻せない事例があります。それぞれどんなケースが当てはまるか見ていきましょう。
取り戻せる事例
被相続人の意思に基づく財産の使用ではないと証明できる場合には、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」を行うことができます。つまり、相続財産を取り戻すには使い込みがあったことを示す証拠資料が必要となります。
使い込みの証拠となる資料
証拠となる情報には以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人の預金口座の取引明細書
- 被相続人名義の銀行口座から引き下ろす際の伝票・委任状
- 被相続人所有の不動産の売買契約書
- 被相続人名義の株式の取引明細書
- 使い込みが行われた時期における被相続人の診断書、入通院履歴、カルテ、介護認定資料、介護記録など
被相続人の通帳が手に入らない場合は、金融機関で取引履歴を取得することができます。また、窓口で引き出しが行われたのであれば、払戻請求書などの書類に手続きをした人の筆跡が残っている場合もあり、有益な資料となることもあります。弁護士に依頼すると、弁護士会照会制度を利用して各金融機関における預貯金の取引明細書を効率よく取り寄せることも可能です。
しかしながら、通帳や取引履歴によって多額の預貯金の引き出しが確認されただけでは使い込みに対する返還請求は認められません。被相続人本人が生前に出金していたり、本人の意思で人に頼んで引き出しを行ったりした場合は使い込みとは言えないからです。被相続人の意思による引き出しではないことを証明するためには、当時の被相続人が外出できる身体状況であったか、認知症を患っていた場合にはその重症度がどの程度であったかなどを示す医療・介護関係資料が必要となります。医療関係の資料は一定期間が経過すると廃棄されてしまうため、早めに取り寄せましょう。
話し合いで解決を図るにせよ、弁護士に依頼して裁判で解決するにせよ、これらの証拠資料は客観的な判断を下すために必要となります。
取り戻しができない事例
一方、使い込みをした人物に返還や損害賠償をする支払能力がない場合や、すでに時効が成立している場合などには、相続遺産の使い込みが事実であっても取り戻しが困難となります。
相続財産の使い込みを立証するには時間がかかる上に、不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権には時効があります。権利が時効消滅してしまうリスクを防ぐためにも、迅速に行動を始めることがポイントです。
不当利得返還請求権の時効は5年または10年
不当利得返還請求権は、法律上の正当な理由なく利益を得て他人に損害を与えた人物に対して、不当に得た利益の返還を請求する権利です。「権利行使できると知った時から5年間」または「権利の発生時から10年間」で時効を迎えます。相続財産の使い込みの場合、債権者が使い込みの事実を知った日から5年以内、他の相続人による使い込みがあった日から10年以内に請求をする必要があります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は3年
不法行為に基づく損害賠償請求権は、故意または過失によって他人の権利や利益に損失を与えた人物に、その損失や損害に対する賠償を請求できる権利です。時効は「損害及び加害者を知った時から3年」と定められています。使い込みの事案では、相続財産の使い込みが発覚してから3年以内に請求しなければなりません。
相続財産の使い込みを取り戻す手続きの流れ

証拠資料を集めて使い込みがあった事実が明確になったら、まずは相手方と話し合いの場を設けて交渉を試みます。その後、直接的な交渉で解決できるのか、家庭裁判所での調停を図るのか、地方裁判所へ訴訟の提起が必要となるのかといった対応を、証拠状況や相手方の態度によって検討する流れとなります。
一般的な手続きの手順について解説していきますが、どのように解決を図るのが最適かは事案によって異なるため、弁護士に相談してアドバイスを受けたり第三者として交渉を依頼したりするといいでしょう。
相手方との話し合い
話し合いの場では、相手方に疑われる出金や横領についての説明を求め、その説明が合理的か、証拠があるかなどについて確認します。その後、請求額を明確にして財産を返還するよう求めます。請求額は使い込まれた金額だけでなく相手の支払能力も考慮し、支払い可能な金額を交渉することになります。双方の合意が取れたら合意書を作成し、分割払いで返還する場合には公正証書にすることが大切です。
ただし、当事者間の話し合いでは相手方が協力的でないケースも多く、説明を拒否したり不合理な説明しかなかったりすることもあります。また、相続財産をめぐるトラブルは双方とも感情的になりやすく、合意に至らない可能性があります。弁護士に任せることで法的根拠に基づいて的確に交渉を進めることができ、相手の責任を明らかにして返還への合意を取れる可能性が高まります。
遺産分割調停
相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる姿勢がある場合や、使い込みの金額がそれほど大きくない場合には、訴訟を提起せずに遺産分割調停の中で解決を図る方法も考えられます。遺産分割調停では、相続人全員の同意があれば、使い込まれた相続財産が存在するものとして遺産分割ができる可能性があります。証拠に基づいて使い込みの事実を証明し、使い込みをした金額を公正に計算することが重要です。
裁判所に訴訟を提起
交渉や調停で解決することができない場合には、地方裁判所に訴訟を提起することとなります。相続財産の使い込みに対する裁判は「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」が用いられますが、どちらで主張を行うかによって主張の仕方や法的構成が異なってきます。どちらの主張が利益となるかは個々の案件によってそれぞれですので、法律的な目線からの検討が必要です。
相続財産の使い込みが発覚したら弁護士にご相談を
相続財産の使い込みが疑われる場合に取るべき手続きについてご紹介しましたが、これらの手順の中には法的な手続きに慣れていない方にとっては判断が難しい場面も多く発生します。収集した証拠資料で立証ができるのか、どのような手続きを選択すべきかなど、不安な点を抱えたまま解決を急ごうとすることはおすすめできません。使い込みを取り戻すには時効がある以上、迅速かつ的確に手続きを進める必要があります。
弁護士に依頼することで、事実調査や証拠集め、相手方との交渉、訴訟、遺産分割の相談まで任せることができます。相続財産の使い込みをめぐるトラブルによって、相続人同士の関係性が壊れてしまうケースも少なくありません。第三者が客観的な目線で当事者の間に立つことで、よりスムーズな解決を目指すことができます。適切な解決を図るためにも、まずはお早めに弁護士にご相談ください。
半田みなと法律事務所は、相続財産に関するご相談を多くいただいており、実績も豊富です。解決事例も公開しておりますのでぜひご覧ください。
「相手方の使途不明金を主張し、法定相続分よりも多い約2500万円分の相続財産を取得」
「不仲兄弟で話ができなかったが、弁護士が遺産分割協議の交渉をした結果1400万円を相続」
初回のご相談は60分無料となっております。2回目以降は30分5,500円(税込)となっておりますが、ご相談後に受任させていただいた場合は、弁護士費用より初回相談料をお引きいたします。お問い合わせページより、電話やメールにてお気軽にご連絡ください。