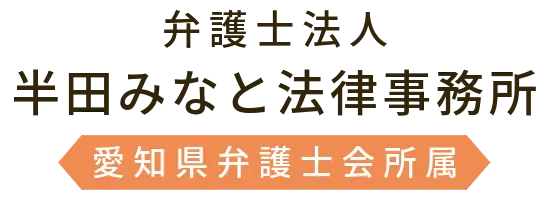遺産の分配について親族で話し合い、やっと遺産分割協議書を作成したものの、相続人の1人がその内容を守らずトラブルになる事例もあります。
「自分が相続した財産が引き渡されない」「親の介護が条件だったのに実行しない」など、約束を守らない相続人がいる場合でも、一方的に遺産分割協議書の内容を撤回することはできません。ではどのように対処するのがいいのでしょうか。
今回は、遺産分割協議書の内容が守られない事例としてよくあるケースや、約束を守らない相続人がいる場合の対処法、そのようなことが起きないように事前にできる対策について解説します。
遺産分割協議書の内容が守られない場合によくある事例
遺産分割協議書の内容が守られない事例は、以下の3つのパターンに大きく分けられます。
代償金が支払われない
不動産や会社事業など、現金で分割できないものを相続する人は、他の相続人に対して代わりとなる金銭を支払います。この遺産分割の方法のことを「代償分割」、支払われるお金のことを「代償金」と言います。例えば、自宅などの不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に応じた代償金を支払うといった形で遺産分割が行われます。
しかし、遺産分割協議で代償分割をすることが決められたにも関わらず、代償金の支払いがされないという事案は多くみられます。
不動産が引き渡されない
遺産分割協議で不動産を相続することが決まったら、不動産の引き渡しを受けることになります。しかし、遺産分割前からその不動産に住んでいた別の相続人が居座ってしまい、さまざまな理由を付けて引き渡しに応じないというケースも多くあります。
親の介護をしない
遺産分割協議で、高齢の親の介護をするという条件のもと、他の相続人よりも多く遺産を相続するケースもあります。しかし、実際には相続はしっかりと受けたにも関わらず、親の面倒を見ないという相続人もいます。
遺産分割協議書の内容が守られなくても撤回はできない!対処法は?
協議の約束が守られないトラブルが起きても、そのことを理由に一方的に遺産分割協議書の内容を撤回することは原則としてできません。過去に最高裁判所によって以下のような判決がありました。
- 遺産分割は協議の成立とともに終了する。その後、相続人同士の債権債務の関係について問題が起きた場合は、相続人同士で解決を図る必要がある
- 遺産分割協議の解除によって法的安定性が著しく害されるため、解除は認められない
遺産分割協議が成立すると、相続開始の時点にさかのぼって効力が発生します。つまり、遺産分割協議によって、それぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)から直接財産を相続したものとして扱われます。遺産分割協議が解除されると、改めて相続開始時までさかのぼって遺産を再分割できることになりますが、そのようなことを繰り返すといつまで経っても遺産分割ができません。法的に不安定な状況が続いてしまうのを防ぐために、遺産分割協議の解除は認められていないのです。
では、遺産分割協議書の内容を守らない相続人にはどのように対処すべきでしょうか。対処法を1つずつ解説していきます。
遺産分割協議書の内容を守るよう交渉する
まずは、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書に書かれた約束を守って履行するよう粘り強く交渉しましょう。
トラブルが起きている以上、相手方が任意に代償金の支払いや不動産の引き渡しをする可能性は低いかもしれません。しかし、不履行の状態が続くのであれば調停や訴訟を申立てるしかないことをしっかりと伝え、相手に心理的なプレッシャーを掛けるなど、できることを実行しましょう。当事者同士の話し合いは感情的になりやすいため、弁護士など第三者に依頼して交渉をしてもらうことで、スムーズな解決を図る方法もあります。
遺産分割協議のやり直しができる場合には検討する
話し合いで解決しない場合には、遺産分割協議のやり直しができないか検討してみましょう。遺産分割協議書の内容を一方的に撤回することはできませんが、例外的に遺産分割協議をやり直せる場合があります。そのためには以下のような条件を満たすことが必要です。
- 相続人全員が納得した上で再協議した
- 遺産分割協議の際に詐欺や強迫が行われていた
- 遺産分割の重大な内容について勘違いをしたまま遺産分割協議をした
- 遺産分割協議の内容が公序良俗に違反する
- 資格のない人が遺産分割協議に参加していた
相続人全員ということは、遺産相続協議書の内容を守らない相続人も含めて話し合い、納得した上で遺産分割方法を決め直す必要があります。相続分が減ってしまう可能性が高い交渉に対して、協力的に再協議に応じてくれると考えるのは現実的ではないでしょう。
また、遺産分割協議をした際に他の相続人から詐欺や強迫を受けたり、錯誤があったりする場合には遺産分割協議の取り消しが可能となります。違法行為を前提とした相続など、公序良俗に反する内容である場合には、遺産分割協議自体が無効となります。
遺産分割協議に参加する資格のない人とは、相続放棄・相続分の譲渡をした相続人、認知症などによって意思能力がない相続人などが挙げられます。そのような人が参加していた場合も、遺産分割協議は無効になります。いずれの場合でも遺産分割協議のやり直しをすることができます。
遺産分割後の紛争調整調停を申し立てる
話し合いでも交渉ができず、遺産分割協議のやり直しも難しい場合には、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。
遺産分割後の紛争調整調停では、成立した遺産分割協議の内容に不満がある場合や、協議の内容が守られない場合に、家庭裁判所の調停委員が間に入ってトラブルの解決を図ります。調停ですのであくまでも当事者同士の話し合いとなりますが、調停委員が双方のやり取りを伝えるので、相手方と直接顔を合わせる必要がなく、冷静に円滑に話を進めやすいでしょう。ただし、調停で双方の合意を得られなかったり、相手方が欠席したりする場合には、調停は不成立となり終了してしまいます。
訴訟を提起する
遺産分割後の紛争調整調停が不成立となった場合や、相手方の協力的な姿勢が望めず調停の申立てをしなかった場合などには、地方裁判所へ訴訟を提起します。代償金の支払いがない場合には代償金の支払い請求訴訟、不動産の引き渡しがない場合には所有権に基づく不動産の明渡し請求訴訟を提起することになります。
訴訟を提起した場合、裁判官から当事者間での和解を勧められることも多いですが、和解が成立しなければ判決が言い渡され、双方にその判決に従う義務が生じます。それでも相手方が判決に従わない場合には、相手方の財産に対して強制執行が行われるケースもあります。
扶養料請求調停を申し立てる
不履行の内容が親の介護である場合、訴訟によって強制的に介護をさせることは難しいでしょう。その場合の手段として、扶養料請求調停の申し立てが考えられます。
扶養料とは、扶養を受ける人の生活費のことです。親の介護を条件に遺産を多く相続したのに介護をしようとしない事案の場合、相手方には親族として親の扶養料を負担する義務があることになるため、親から扶養料を請求することができます。
ただし、扶養料の請求が認められて支払われたとしても、相手方に介護をさせることは強制できません。親が自分で身の回りのことをできない場合には、誰がどのように世話を行うか改めて親族間で協議する必要があるでしょう。
相続に関するトラブルは、親族間で直接話し合いをしても難航することが多いです。今後の関係性に支障をきたさないようにするためにも、早めに弁護士に相談することもご検討ください。
遺産分割協議成立後のトラブルを防ぐための対策

遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいるトラブルが起きると、協議にかけた時間や労力が無駄になるだけでなく、調停や訴訟で解決するためにさらなる時間をかけることになります。このようなトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を書いておくことと、遺産分割協議書を公正証書で作成することという2つの対策が有効です。
生前に遺言書を書いておく
生前に遺言書を書き、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、被相続人の死後に遺言書の内容を実現するために、名義変更や払い戻しなどの手続きを行う人のことです。
被相続人の遺言書があれば、そもそも遺産分割協議をしなくても相続財産を分配することができます。さらに遺言執行者を定めておくことで、遺言で指定されたことを守らない相続人に対しても必要な手続きを行うことが可能です。
遺言執行者は相続人の中から指定することもできますが、遺言を確実に実現するためには客観的な立場で動くことも必要ですので、利害関係のない第三者に依頼することをおすすめします。一般的には、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼することがほとんどです。
遺産分割協議書を公正証書で作成する
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことです。遺産分割協議書を公正証書で作成する際には、債務を履行しない場合には強制執行に従うという文言を記載しておきましょう。公正証書で作成した遺産分割協議書を根拠にすることで、訴訟を起こすことなく強制執行の申し立てをすることが可能となります。
ただし、公正証書で強制執行ができるのは金銭債権に限られるため、不動産の引き渡しに関しては、遺産分割協議書を公正証書で作成しても強制執行を行うことはできません。その場合には別の方法で債務名義を得る必要がありますが、どのような方法があるかはケースによって異なります。弁護士にご相談ください。
遺産分割協議書の内容が守られない場合は専門家にご相談を
遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいるトラブルでは法的な解決を図るケースが多く、膨大な時間と費用が必要となります。トラブルが解決するまでの精神的な負担も軽いものではないため、事前に対策できるタイミングで手を打っておくことがポイントとなります。
相続トラブルへの対策や、すでに起きてしまった問題の解決でお困りの場合は、相続トラブルへの知識や実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。半田みなと法律事務所では、遺産分割協議や生前贈与などに関するご相談も多くいただいております。初回のご相談は60分間無料ですので、お問い合わせページより、電話やメールにてお気軽にお問い合わせください。