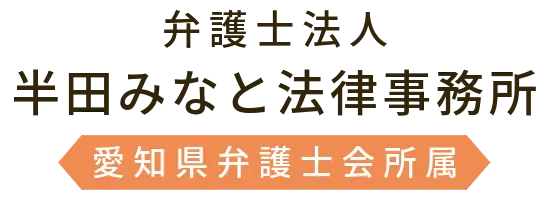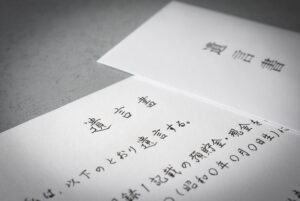「相続財産が想像していたよりも大幅に少ない」
「生前あると聞いていた財産がないことになっている」
このような場合には、他の相続人による遺産隠しが疑われます。
今回は、遺産隠しが疑われる事例や本来の相続財産の調査方法、遺産隠しが事実であった場合の対処法やその際の注意点などについて、弁護士が解説します。相続財産を公正に分け、全員が納得できる遺産分割ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。
相続財産隠し(遺産隠し)が疑われる事例
遺産隠しとは、被相続人(亡くなった方)の財産を一部の相続人が隠してしまうことです。遺産を隠す相続人がより多くの財産を相続できるようにすることが目的で行われます。
遺産隠しが疑われるケースとして、以下のような事例が挙げられます。
- 被相続人が生前に話していた財産と実際に遺された財産が大きく異なる
- 被相続人の生前にあると聞いていた高価な財産が見つからない
- 被相続人の口座に使途不明の出金が見られる
- 被相続人の通帳を管理している相続人が詳細を見せてくれない
ただし、被相続人の口座に残された金銭が明らかに少ない場合でも、生前に本人の意思によって使われていた可能性もあります。「もっと遺産があったはず」と感情的に動くのではなく、相続財産について客観的に調査し、遺産を隠している事実があるかどうか慎重に検討していきましょう。
遺産隠しが疑われたら調査を!相続財産を見つける方法
遺産隠しが疑われる場合、まずは遺産の内容を正確に把握することがポイントです。しかし、すべての相続財産について一気に探し出す方法はありません。預貯金、不動産、有価証券など、財産ごとに金融機関などをあたってコツコツ調べていく必要があり、非常に根気のいる作業となります。相続財産の具体的な調査方法について解説します。
相続人に確認し開示を求める
遺産隠しが疑われる相続人に、隠している相続財産がないか確認しましょう。本人に直接聞いて確認するだけでなく、税務署に提出した相続税申告書を見せてもらうことも考えられます。
しかし、相続人が他の相続人に対して遺産を開示する義務は法律上ありません。本当に相続人が遺産隠しをしているなら、確認されても簡単に真実を話す可能性は低いでしょう。
預貯金について調査する
相続人は、被相続人の預貯金口座の残高証明書や取引履歴を交付してもらうことができます。各金融機関に対して個別に開示を請求する必要があるため、被相続人の口座がある金融機関が明確でない場合には、心当たりのある銀行や信用金庫をあたって特定する必要があります。
交付請求をする際には、相続人であることが確認できる戸籍謄本などの書類、相続人の本人確認書類や印鑑証明書などを用意する必要があります。金融機関によって必要書類や手数料が異なるので、確認しておきましょう。
不動産について調査する
被相続人が所有していた不動産がある場合には、以下の書類やサービスによって調査することができます。
- 固定資産課税台帳(名寄帳・なよせちょう)…不動産がある市区町村役場で開示請求できる
- 登記事項証明書(登記簿謄本)…法務局の窓口や郵送などで請求できる
- 登記情報提供サービス…インターネットで登記情報を確認できる
- 固定資産税納税通知書…被相続人宛てに郵送されたものを確認する
固定資産課税台帳によって、その自治体に所在する被相続人所有の不動産に関するすべての情報を確認できます。ただし、固定資産課税台帳では市区町村をまたいで情報を確認することはできません。近隣自治体や被相続人の故郷、かつて居住していた地域など、被相続人が不動産を所有している可能性がありそうな市区町村すべてに申請することも検討しましょう。
自治体から被相続人宛てに郵送された固定資産税納税通知書から不動産の情報を知ることもできますが、通知書に記載が漏れている不動産が存在したり、相続人が通知書を処分していたりするケースもあります。
株式など有価証券について調査する
株式や投資信託といった有価証券や暗号資産などについては、被相続人が口座を所有していた証券会社に個別に問い合わせることで、資産状況の照合を依頼することができます。
書類が残っていれば証券会社を特定しやすいですが、ネット証券を利用しているケースも増えていますので、被相続人のアプリなども確認して漏れなくチェックすることがポイントです。また、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせて口座開設状況を確認することもできます。
遺産隠しが判明した場合の対応方法
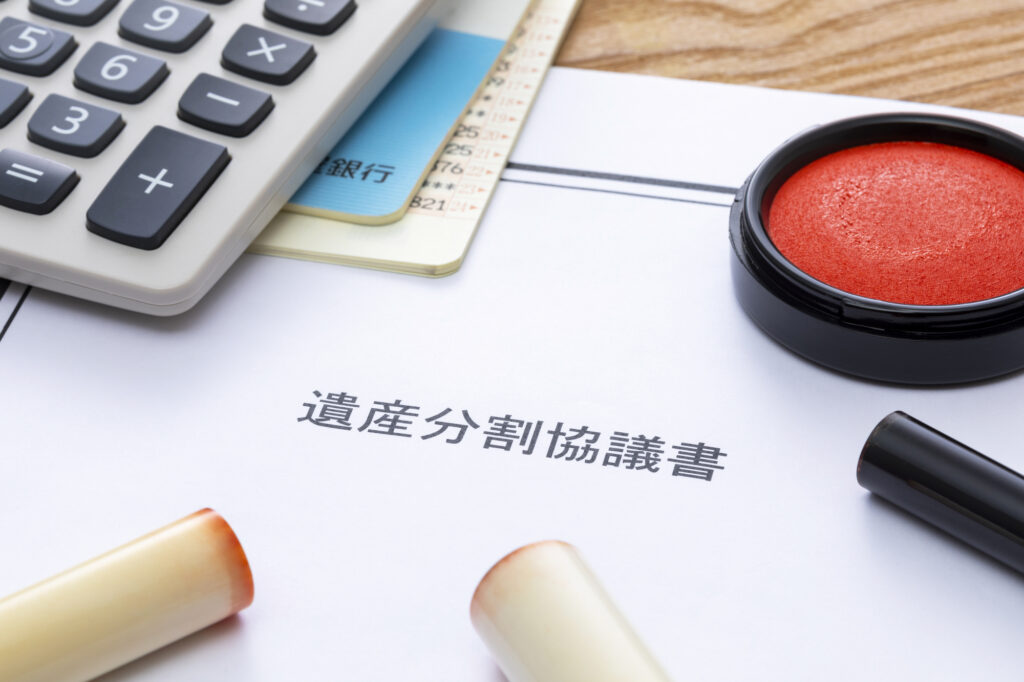
遺産分割協議の前に遺産隠しが疑われた場合、迅速に相続財産の調査をして正確な財産目録を作成してから協議をすべきです。しかし、実際には協議が終わってから遺産隠しが発覚することもあるでしょう。遺産分割協議後に遺産隠しが発覚した場合には、以下のような対応方法が考えられます。
隠されていた財産だけを対象に遺産分割協議を行う
遺産分割協議の後で新たな財産が見つかったら、隠されていた相続財産のみについて相続人同士で遺産分割協議をすることができます。
ただし、隠されていた相続財産の価値がとても高く、遺産分割の内容に影響を及ぼす場合や、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意する場合には、協議をやり直すことも可能です。
遺産分割協議をやり直す
遺産隠しによって他の相続人が相続財産について誤解した状態で遺産分割協議に同意したケースでは、詐欺や錯誤があったと認められる場合があり、遺産分割協議内容の取り消しや無効を主張することができます。遺産分割協議の取り消しが認められれば、協議のやり直しが可能です。また、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議をやり直すこともできます。
しかし、詐欺や錯誤があった旨を主張しても遺産を隠している相続人に反論されたり、一部の相続人の同意が得られなかったりして、協議のやり直しができない可能性もあります。相続人同士の話し合いによって遺産分割協議のやり直しをすることが難しい場合には、裁判所で調停や訴訟を提起し、協議のやり直しを図ることになります。まずは家庭裁判所での調停を行い、調停が不成立になったら訴訟を提起する流れです。法的な手続きとなりますので、弁護士に依頼して進めましょう。
不当利益返還請求を行う
不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく利益を得た場合に、その利益の返還や与えた損害への賠償を求める手続きのことです。遺産隠しが発覚して遺産分割協議をやり直す場合、まずは隠されていた相続財産を不当利得返還請求によって取り戻す手続きが必要です。
また、遺産分割前に、遺産を隠していた相続人によって相続財産が無断で使い込まれており、遺産分割協議時にはすでに相続財産の一部がなかったという場合にも、他の相続人は使い込んだ相続人に対して不当利得返還請求を行うことができます。
遺産隠しへの対応についての注意点
遺産隠しが発覚し、遺産分割協議のやり直しを検討する際には、注意点も頭に入れておきましょう。特に時効については時間との戦いですので、手続きを迅速かつ的確に進めるためにも、弁護士など専門家の力を借りることが必要となります。
時効がある
遺産分割協議の取消権や不当利得返還請求権には、それぞれ時効があります。以下の期間が経過すると権利が時効消滅してしまうので、注意が必要です。
遺産分割協議の取消権の時効は5年または20年
遺産分割協議を取り消す理由が詐欺や錯誤である場合、取消権には時効があります。取消事由を知ってから5年、または遺産分割協議が行われた日から20年が経過した時点で、権利は消滅します。つまり、遺産隠しが判明した時点から5年以内、遺産隠しが行われた時点から20年以内に遺産分割協議の取り消しを行う必要があります。
不当利得返還請求権の時効は5年または10年
不当利得返還請求権の時効は、権利行使できると知った時から5年、または権利の発生時から10年です。遺産隠しのトラブルの場合は、遺産隠しが判明した時点から5年以内、遺産隠しが行われた時点から10年以内に請求をする必要があります。
ただし、取消権や不当利得返還請求権を行使する旨が書かれた内容証明郵便を、遺産隠しが疑われる相続人に送付することによって、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。遺産隠しを知ったら早い段階で手続きを進める準備を始めましょう。
税金が二重に発生する可能性がある
通常は、遺産分割協議の結果に従って相続税が課税されます。しかし、相続人全員の合意によって遺産分割協議をやり直し合意する場合、最初の協議内容に基づく相続税と、2度目の協議内容に応じた贈与税が発生する可能性があります。二重に課税されることになってしまうのです。
また、やり直した協議で決定した遺産分割方法によっては、控除などを適用できず相続税額が上がってしまう可能性もあります。相続税が増加する場合には修正申告が必要です。申告をしないと過少申告加算税が課されることもあります。
相続財産が高額となる場合には、相続に関する税金についての知識を付けておいたり、相続問題に詳しい弁護士に依頼して確認してもらったりすることをおすすめします。
使い込まれた遺産は回収できない可能性がある
遺産隠しが発覚したけれど、その財産は遺産分割をする前にすでに使い込まれてしまっていたという事案もあります。その場合に使い込まれた遺産を回収する手段はいくつか考えられます。例えば、相続人全員の同意があれば使い込まれた遺産も存在すると見なして遺産分割を行うことができます。また、相続財産を使い込んだ相続人に対して、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことも検討できるでしょう。
しかし、相続財産を使い込んだ相続人にお金がまったくないなど、支払い能力がない場合には、使い込まれた遺産を回収することは現実的に困難となる可能性もあります。
相続財産の使い込みについて詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
遺産隠しが疑われる場合は早い段階で弁護士にご相談を

遺産隠しに対して取れる手段には時効があるものもある以上、迅速かつ的確に対応を進める必要があります。財産の調査や法的な手続きには時間がかかり、法的な知識が必要となる場面も多いため、スムーズに進めるためにも早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士に依頼することで、弁護士会を通して官公庁や金融機関に照会することができるので、自分では探せなかった情報を見つけることができます。弁護士が財産の調査を代行したり、遺産分割協議の調整をしたり、調停や訴訟に対応したりすることも可能ですので、相続問題にかかる時間的・精神的な負担を大きく軽減することができるでしょう。遺産隠しが疑われる相続人との交渉を弁護士に任せることで、相手に事実を認めさせやすくなるなど、トラブルの早期解決を図ることもできます。
半田みなと法律事務所では、遺産相続や成年後見に関するご相談を多くいただいており、実績も豊富です。初回のご相談は60分間無料ですので、お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。