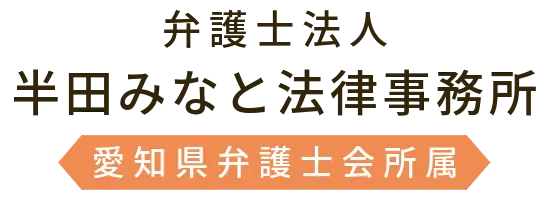昨今、高齢となった親の囲い込みが増加しています。親と同居している兄弟姉妹が親に会わせてくれないということは精神的な苦痛です。親にとっても、他の子どもや親族が会いに来てくれないのはとても寂しくつらいことでしょう。それに加えて、囲い込みをしている親族が親の資産を使い込んでしまったり、自分に有利な遺言書を書かせたりするなど、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
囲い込み問題が起きても、親が動いて解決することは困難であるケースも多いです。囲い込みが長期化する前に早期の解決が求められますが、囲い込みをしている親族が協力的でないことが想定されますので、どのような方法で対応するにしても法的な手続きなしに進めるのは難しいでしょう。
今回は、囲い込みの目的やよくある事例、対応策について弁護士が解説いたします。囲い込みの長期化や具体的な遺産相続トラブルの発生を防ぐために、早急に対策の手を打ちましょう。
囲い込みをするのはなぜ?よくある事例
囲い込みとは、高齢の親の面倒を見ている子どもや親族が、親と他の親族との交流を一切排斥してしまうというトラブルです。
親が高齢になった時、子どもが親を介護しながら一緒に暮らすこと自体は一般的なことで、何も問題はありません。しかし、親を引き取った方が他の親族と親を一切会わせようとしないケースが発生することがあり、これが問題となっています。
囲い込みが起きる理由や目的
高齢の親を囲い込む理由はさまざまですが、親の遺産が目当てである事例が多く見られます。親の介護を理由に親と同居し、他の親族と直接コミュニケーションができないような環境を整え、自分にとって有利な遺産相続をすることが目的となっています。
囲い込みを受ける親は肉体的・精神的に衰えている場合も多く、経済的に弱い立場であることもあり、自らの意思で助けを求めることが困難です。子どもに同居を解消すると言われてしまわないか不安だったり、自分では身の回りのことができないと心配だったりして、囲い込みを受けているとわかっていても、自ら対応しにくいというケースもあります。また、親が認知症を患っている場合には、自分がひどいことをされているという自覚がないかもしれません。
囲い込みが疑われる場合でも、親をその環境から連れ出すことは難しいでしょう。兄弟や親族の家であっても、親を連れ出すためであっても、勝手に立ち入れば犯罪行為となってしまいます。囲い込みのトラブルでは、親の意向を尊重して無理強いをしないことが大切です。まずは親が今どんな状況にあるのか、その状況をどのように感じているか、具体的に把握する必要があります。その上で適切なサポートを検討していきましょう。
囲い込みでよくある事例
囲い込みは遺産相続トラブルの前哨戦とも捉えることができます。囲い込みについてよくある事例をご紹介します。
- 親と同居している兄弟姉妹が「嫌がっている」「会いたくないと言っている」など理由を付けて親に会わせてくれない
- 親がいつの間にか老人ホームに入れられていて、どこにいるか知らされていない
- 病気で入院している高齢の親族のお見舞いに行こうとしたが、他の親族が入院先を教えてくれず連絡できない
- 認知が進んでいる親に後見人を付けたいが、同居している兄弟姉妹が拒否する
- 同居している親族が親の財産管理状況について教えてくれない
- 高齢の親が、理由もなく不動産を知らないうちに売却してしまっていた
これらの事実があると囲い込みが疑われます。蓋を開けてみると親の資産が使い込まれていたり、不動産を売って贈与されたり、囲い込みをした人物に有利な遺言書や生前贈与をさせていたりと、大きなトラブルにもなりかねません。
相続財産の使い込みについて詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
囲い込みへの対応策として囲い込みをされた親に後見人を付けることはできる?
後見人(成年後見人)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の代わりに、財産管理や日常生活上必要な契約などの法律行為をする権限を持つ人のことです。
親に後見人が付いていれば囲い込みをされても財産を守ることができますが、すでに囲い込みをされている状態の親に後見人を選任することは困難です。後見人を選任するには家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、その際に被後見人(親)の精神状態や判断能力を明らかにする診断書を添付します。しかし、すでに囲い込みをされて親に面会できない状態では、診断書を作成するために病院に連れていくことは難しいでしょう。診断書がない状態で申立てをしたとしても、裁判官は診断書に基づく被後見人の精神状態に応じた成年後見制度を選択することになるため、申立てが却下となる可能性が高くなります。
しかし、弁護士に依頼することで、例外的に過去の診断書や介護認定時の記録などで申立てを行えるケースもあります。ただし、一度後見人の申立てをすると原則として取下げられないことや、後見人が選任されると報酬の支払いが発生し、途中で勝手に止めることができないことなど、注意点もあります。後見人の選任がベストな解決策となるのかは案件によって異なりますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
囲い込みへの対応策は他にも!専門家との協力が必須

後見人の選任以外にも、囲い込みへの対応策はいくつかあります。しかし、後見人の選任を含めて、どの手段をとるにしても弁護士のサポートなしで進めることは困難です。また、囲い込み問題はケースによって最適な解決策が異なり、囲い込みをされている方の意思も関係してきますので、対応に正解はありません。どの方法で対応していくのが適切か、手続きをどのように進めていくか、弁護士に相談することをおすすめいたします。
行政機関への連絡・連携
まずは行政機関と連携をするという手段が考えられます。行政には、高齢者が虐待を受けている場合、高齢者を保護し尊厳を守るために適切な措置を取る義務があります。この場合の虐待とは、身体的虐待、介護や世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が該当し、囲い込みがそれに当てはまると判断されれば、親族と親を分離して施設入所の措置を取ってくれる可能性もあります。
囲い込みをしている親族によって金銭の搾取がある場合には経済的虐待が疑われますので、自治体の地域包括センターなど、行政機関に相談しながら解決を図ることも有効です。
親族間の紛争調整調停
親族間の紛争調整調停とは、親族間の対立や紛争を解決して円満な関係を回復するための話し合いの場として利用される調停手続で、家庭裁判所によって行われます。双方から聴いた情報や当事者から提出された資料などから事情をよく把握して、解決に向けた助言を受けられます。
囲い込みの根本的な原因が親族間の対立によるものであれば、事実をもとに第三者を介した調停の場を設けることで対立関係を解消し、囲い込みの解決が望める可能性があります。しかし、調停はあくまでも話し合いの手続きです。囲い込みをしている親族が出席しない場合などには不成立となるため、双方が協力的でないと調停だけで解決することは難しいでしょう。
面会妨害禁止の仮処分
仮処分とは、裁判所で行われる暫定的な処分のことです。正式に裁判を起こして判決を得るまでには、1年程度かかるのが一般的です。しかし、囲い込みに関して1年も待っていては、親の財産の使い込みが深刻化する可能性があり、親の身体や心の状態も悪化しないか心配です。こうした状況では、裁判を起こす前に、裁判所が迅速な手続きによって一定の地位を認める場合があります。これを仮処分と呼びます。
面会妨害禁止の仮処分が決定すれば、囲い込みをしている親族に対して裁判所が面会妨害を禁止しますので、法的に当面の面会が可能となります。ただし、面会妨害禁止の仮処分を認めてもらうのは簡単ではありません。実際に平成30年の事案では、面会妨害禁止の仮処分を出す前に、他の手段で面会できるように家族が試行錯誤する必要があるという判決となりました。行政機関との連携や親族間の紛争調整調停、後見人選任の申立てなど、できる手段を尽くしても面会が叶わない場合に面会妨害禁止の仮処分を申立てを検討しましょう。
損害賠償請求
囲い込み自体を解消する方法ではありませんが、囲い込みをする親族に損害賠償請求をすることも可能です。親と自由に面会交流する権利は法的に保護されており、囲い込みによってその権利を侵害され、親との面会を拒否されたことによる精神的な苦痛に対して損害賠償を請求する形となります。損害賠償請求が認められれば、囲い込みをしている親族の対応に変化があるかもしれません。囲い込みの解決を間接的に促す効果が期待できるでしょう。
囲い込みが疑われる場合には弁護士に相談を
高齢の親が他の親族に囲い込みをされ、居場所が不明になったり連絡が取れなくなったりする場合には、長期化を防ぐためにも早めに弁護士に相談しましょう。
使い込まれてしまった財産を取り戻すには膨大な時間と労力が必要となります。まして親が亡くなってしまった後では、囲い込みをしていた親族によって勝手に作成された遺言書であっても、被相続人の意思に基づくものかどうか証明することが難しく、遺言が無効であることを主張するのが困難となるケースもあります。囲い込みが疑われる場合には、具体的なトラブルが生じる前に早急に手を打つことが重要です。
高齢の親を囲い込みから救うことができるのは親族だけです。囲い込みではないかと気付いたら、すぐに弁護士と協力して対応策を検討しましょう。
半田みなと法律事務所では、遺産相続や成年後見に関するご相談を多くいただいており、実績も豊富です。初回のご相談は60分間無料ですので、お気軽にお問い合わせください。2回目以降は30分5,500円(税込)となっておりますが、ご相談後に受任させていただいた場合は、弁護士費用より2回目の相談料をお引きいたします。お問い合わせページより、電話やメールにてお気軽にご連絡ください。