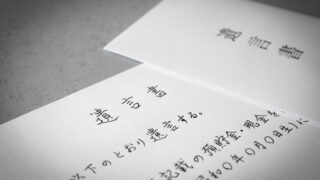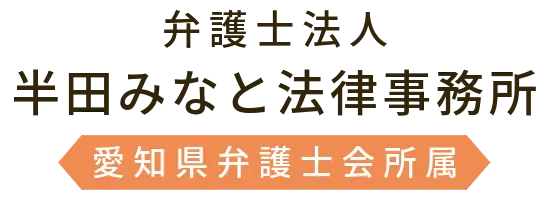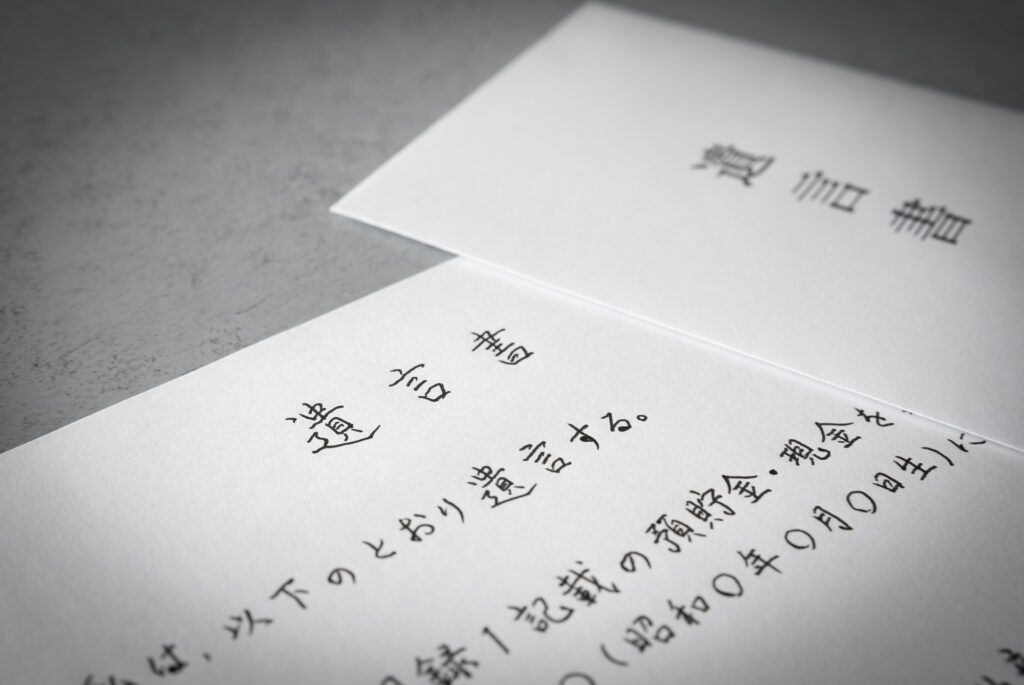
「遺言書の内容に納得できない…これって本当に有効?」
このような不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言書として残っていると、一見有効に思えるかもしれませんが、法律上の要件を満たしていなければ、無効と判断されることもあります。
本記事では、半田市を中心とした知多半島エリアにお住まいの方に向けて、遺言が無効になるケースやその対応方法をわかりやすく解説します。
次のような疑問を感じている方にも参考になる内容です。
- 署名がないだけで遺言は無効になる?
- 認知症の親が書いた遺言は効力がある?
- 訂正の仕方を間違えると遺言全体が無効になってしまう?
遺言書に不安を感じている方の判断材料として、ご活用いただければ幸いです。
遺言が無効と判断される主なケース
遺言書に疑問を持ったときに、まず確認したいのが“形式の不備”です。
遺言は法律で細かく形式が決められており、要件から外れていると、どれほど内容がしっかりしていても無効とされることがあります。
ここからは、形式の不備によって無効とされやすい具体的なケースについて、順に見ていきましょう。
署名・押印・全文自書に不備がある
遺言書(自筆証書遺言)には「全文・日付・氏名をすべて自分の手で書き、印鑑を押す」というルールが定められており、どれかが抜けていると、遺言は原則として無効になります(民法968条)。
これは「絶対的要件」とされ、たとえ内容がしっかりしていても、形式が整っていなければ効力が認められないという厳しいルールです。
ただし、署名が名字のみや名前のみでも、遺言者が誰か特定できれば有効になる場合があります。
印鑑は実印ではなく、認印や拇印でも要件を満たすとされています。
他にも、2019年の法改正により、財産一覧を記載する「財産目録」に限っては、パソコンで作成した書類やコピーの添付も認められるようになりました。
このように一部の項目は例外もありますが、“署名・押印・全文自書”の要件は、遺言の有効性を判断するうえで非常に重要なポイントです。
まずはこの項目に該当する不備がないかを確認することが、遺言の有効性を判断する第一歩となります。
日付がない・日付が特定できない

遺言には作成日を明記することが法律で定められており、不備があると無効と判断される場合があります。
具体的には、以下のようなケースが無効となります。
- 日付がまったく記載されていない
- スタンプ印が使用されている(印影のみで自筆でない)
- 「○月吉日」など、具体的な日付が特定できない
一方で「○年○月末日」や「○年の誕生日」など、日付が特定できる表現であれば有効と判断されます。
複数の遺言書が存在する場合には、原則として「一番新しいもの」が有効とされるため、作成日の記載は極めて重要です。
どの遺言書が効力を持つのかを判断するうえでも、日付は欠かせない要素と言えます。
訂正方法が間違っている
遺言の内容を訂正する際には、民法で定められたルールを守る必要があります。
ルールに従っていない訂正は、その部分が無効になるだけでなく、遺言書全体が無効になる可能性もあります。
たとえば、文字を訂正する場合は、以下のような手順を守らなければなりません。
- 該当の文字に二重線を引いて消す
- 訂正した文字を記入する
- 訂正箇所に遺言書で使った印鑑を押す(文字が見えるように)
- 欄外または末尾に「○字削除、○字加入」と記載し、署名する
これらを守らず、修正テープや塗りつぶしで修正してしまうと、内容が読み取れなくなり、訂正が無効とされるおそれが高くなります。
なお、誤字脱字など明らかなミスに限っては、有効と判断された例もありますが、そうしたケースは例外です。
共同で遺言書が作成されている
遺言はあくまで本人が自分の意思で作成するものです。
そのため、夫婦や親子などが1通の遺言書に連名で記載した場合は「共同遺言」とされ、法律上すべて無効になります(民法975条)。
これは、他人の意見に影響されたり、一方の撤回が難しくなったりと、遺言の自由な撤回権に反するためです。
たとえ内容に問題がなくても、共同遺書と見なされた場合は効力が認められません。
ただし、別々の紙に書いた遺言を同じ封筒に入れているような場合は、共同遺言とは見なされず、有効と判断されます。
「1枚の紙に2人分書く」形式には、注意が必要です。
遺言作成時に遺言能力がなかった

「この遺言は本当に本人の意思だったのだろうか?」と疑問に感じる場合、確認すべきなのが「遺言能力」です。
遺言能力とは、遺言を書くときにその内容をきちんと理解し、自分の意思で判断できる力のことを指します。
たとえば、認知症が進んでいて、遺言の内容やその影響をきちんと理解できない状態だった場合は、遺言能力がなかったと判断されます。
しかし「認知症=遺言無効」ではありません。
軽い症状で判断力が保たれていれば有効とされるケースもあり、医師の立ち会いや診断書があれば、遺言能力があったことの証明につながります。
また、遺言書を作れるのは15歳以上と定められており、作成時に15歳未満だった場合も無効です。
遺言能力があったかどうかは、遺言時の心身の状態や言動、遺言の内容などを総合的に見て判断されます。
そのため、遺言能力がなかったことを証明するのは簡単ではありませんが、もし証明できれば、その遺言書全体が無効となります。
第三者に無理やり遺言書を書かされた可能性がある
遺言書の内容が「生前に本人が言っていたことと全く違う」「特定の人にだけ極端に有利になっている」といった場合、誰かに強く言われて書かされた可能性も考えられます。
たとえば、誰かに強く言いくるめられていたり、怖い思いをさせられていたりした場合には、遺言が無効とされることがあります。
ただ、すでに本人が亡くなっているため、こうした事情を証明するのは簡単ではありません。書かれた当時の健康状態がわかる医療記録や、周りの人の証言などが必要になります。
「本当に本人の意思だったのか?」と疑問を感じたら、まずは専門家に相談して、どんな対応ができるのかを確認しましょう。
遺言書作成時の立会人が不適格である
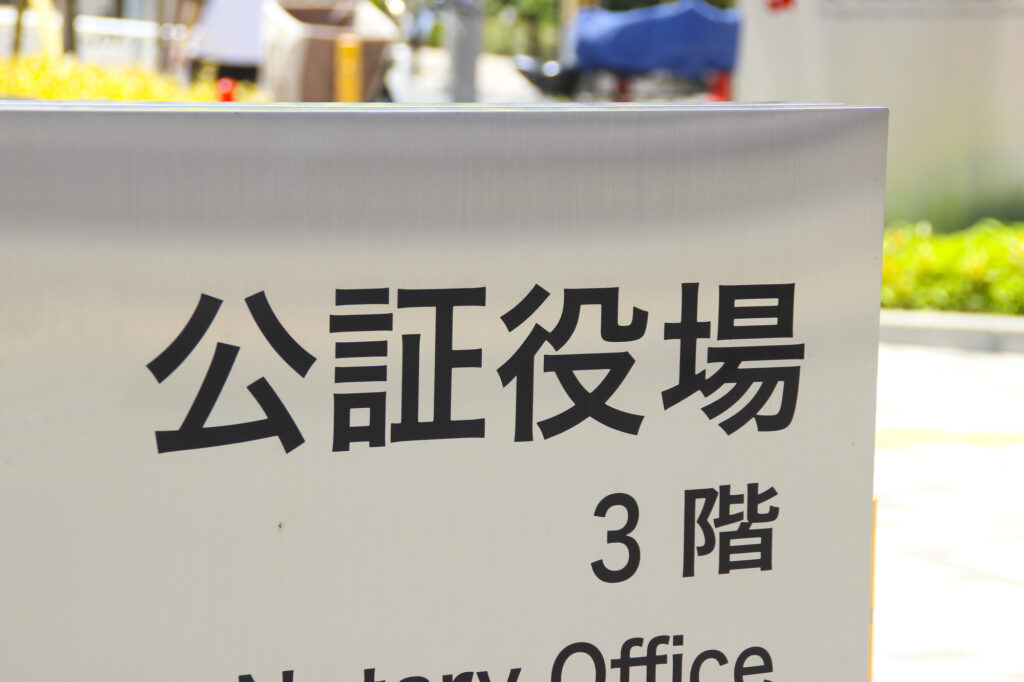
「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する場合には、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が内容を聞き取って作成するものであり、秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られないまま、公証役場で封印・証明する形式のものです。
ただし、誰でも証人になれるわけではなく、未成年者や相続人、その配偶者、公証人の関係者などは証人として認められていません。
もし証人として不適格な人が立ち会っていた場合、遺言書が無効になる可能性があります。
「親族が立ち会っていた」と聞いた場合は注意しましょう。
内容が明確でない
遺言書では「どの財産を、誰に、どのように渡すのか」を具体的に記す必要があります。
たとえば「銀行預金を子どもに相続させる」とだけ書かれていても、どの銀行口座で、どの子どもなのかが不明確な場合、その部分は無効と判断されるおそれがあります。
また「お世話になった人に全て任せる」といった曖昧な表現では、何をどう任せたのかが分からず、遺産分割をめぐるトラブルに発展しかねません。
もちろん、裁判では遺言の趣旨をくみ取るよう最大限の配慮がされますが、遺言者の真意を直接確認できない以上、解釈の仕方によって結論が変わるリスクも残ります。
「文面がはっきりしない」と感じたときは、内容の不備をもとに無効を主張できる可能性もあるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
遺言を無効にしたいときに検討すべき3つの手続き
遺言書の内容に納得できなくても、正式な手続きを取らなければ効力はそのまま残ります。
遺言を無効にするには、法律に基づいた適切な手続きが必要です。
ここからは、状況に応じて検討すべき3つの代表的な方法についてご紹介します。
遺産分割協議:相続人同士で話し合い
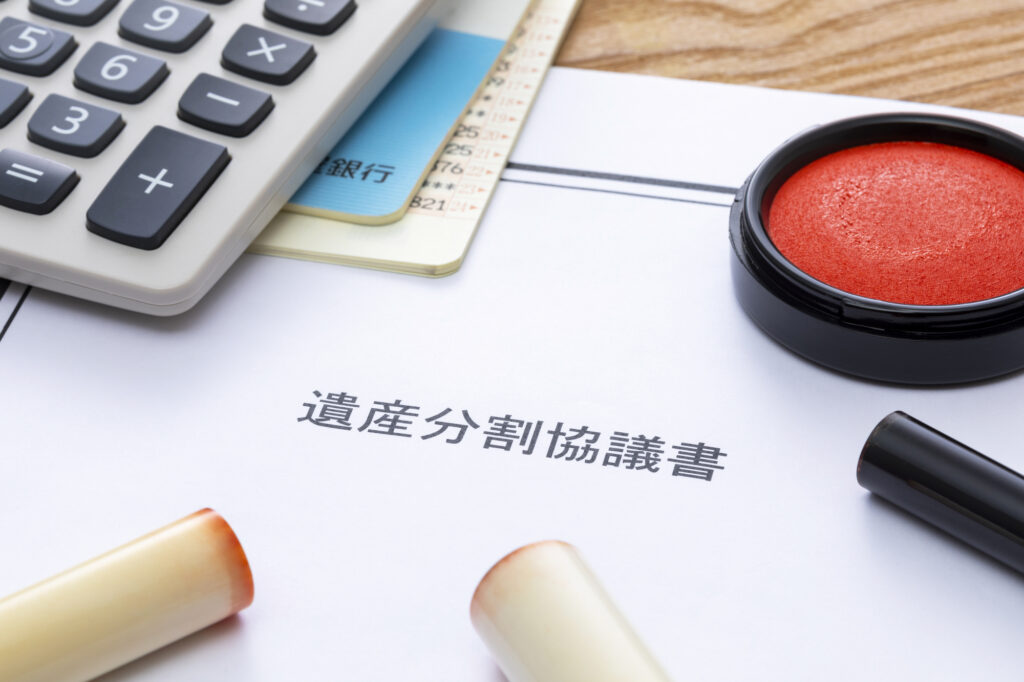
遺言書の内容に疑問があっても、まずは相続人同士で話し合いを行い、遺産の分け方について合意を目指す方法があります。
これは「遺産分割協議」と呼ばれ、通常は遺言がない場合や、遺言で指定されていない財産について活用される手続きです。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言で指定された内容とは異なる分け方をすることも可能です。
遺言書のとおりに分割すると、税務上の不都合が生じたり、かえって親族間でトラブルが起きたりすることもあるため、話し合いで調整した方が円満に進むケースも見受けられます。
調停や訴訟よりも手間や費用を抑えられるため、まずはこの方法から検討すると良いでしょう。
遺言無効確認調停:家庭裁判所での話し合い
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で意見がまとまらなかった場合は、家庭裁判所での「遺言無効確認調停」を検討します。
調停は調停委員を交えて遺言の有効性や遺産の分け方を話し合い、合意を目指す制度です。
半田市をはじめとする知多半島エリアにお住まいの方は、通常、名古屋家庭裁判所半田支部が担当窓口となります。
法律上は、すぐに裁判を起こすのではなく、原則としてこの調停を先に申し立てる必要があります(調停前置主義)。
ただし、話し合いでの解決が難しいと予想される場合は、最初から訴訟を起こすことも可能です。
「遺言は本人の意思ではない」「認知症だったのに遺言がある」など、遺言の有効性に疑問がある場合は、調停を通じてきちんと主張していくことが大切です。
遺言無効確認訴訟:裁判で遺言の有効性について判断を求める手続き

交渉や調停でも合意できなかった場合、最終的な解決手段は「遺言無効確認訴訟」です。
この訴訟は、地方裁判所に対して遺言の有効性を問う手続きで、遺言が法律的に有効かどうかを裁判所に判断してもらいます。
半田市周辺にお住まいの方は、名古屋地方裁判所またはその支部が申立先です。
訴訟の場は、無効を主張する相続人(原告)と、それに反論する相手方(被告)が、証拠や主張を出し合います。
争点として多いのは、遺言能力の有無や、本人が自筆したかどうかといった点です。
医師の診断書や筆跡鑑定などの客観的な資料が、重要な判断材料になります。
最終的に裁判官が遺言が有効かどうかを判断しますが、訴訟の途中で和解に至るケースもあります。
なお、遺言が無効と判断された場合には、改めて遺産分割協議が必要です。
ただし、訴訟にまで発展した相続人同士では冷静な話し合いが難しいこともあるため、手続きの選択や進め方を誤らないためにも、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。
遺言を無効にする手続きで注意すべき4つのポイント

遺言を無効にできるかどうかを検討する際には、誤解されやすいルールや注意点を押さえておく必要があります。
特に「秘密証書遺言」における形式的な例外や、遺言書を勝手に開封した場合の扱い、早めに行動すべき理由、遺留分との関係などは、見落としがちなポイントです。
ここからは、遺言無効に関して知っておきたい重要な注意点を4つ解説します。
1.秘密証書遺言には“自書や日付”に関する例外がある
一般的な遺言書(いわゆる自筆証書遺言)では、全文・日付・氏名を手書きしなければ無効とされますが、「秘密証書遺言」には例外があります。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に伏せたまま、公証人に「遺言書が確かに存在すること」を証明してもらう方法です。
この形式では、遺言書の本文を自筆で書く必要はありません。
また、遺言書そのものに日付が書かれていなくても、公証人が封筒に日付を記載すれば有効とされます。
そのため、一見すると形式に不備があるように見えても、秘密証書遺言であれば無効とならないケースもあります。
半田市周辺にお住まいの方の遺言書であれば、半田公証役場を通じて作成された可能性もあるため、公証人の関与があったかを確認してみると良いでしょう。
2.勝手に遺言書を開封しても無効にはならない
法律では、封印のある遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きを経たうえで開封すべきとされています(民法1004条)。
しかし、誤って開封してしまったとしても、それだけで遺言書が無効になることはありません。
その場合は、家庭裁判所にその旨を伝え、改めて検認を受けましょう。
半田市周辺にお住まいの方は、名古屋家庭裁判所半田支部で検認手続きを行うことが可能です。
なお、所定の手続きを経ずに開封した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります(民法1005条)。
また、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認手続きが不要とされています。
遺言書を見つけた際には、思わず開封したくなるかもしれませんが、トラブルを防ぐためにも、まずは家庭裁判所にご相談ください。
3.遺言無効を争う手続きに時効はないが、早期対応が重要

「遺言無効確認」の調停や訴訟には、明確な時効の期限はありませんが、トラブルを防ぐためにもできるだけ早めの対応が大切です。
時間が経つにつれて、立証に必要な証拠や資料が失われてしまう可能性があります。
たとえば、医師の診断書や関係者の記憶などは、時間とともに入手や証明が難しくなるため、早い段階での対応が求められます。
また、遺言が有効とされた場合に備えて、遺留分をめぐる対策も早いうちから視野に入れておきたいところです。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことで、たとえ遺言によって全財産を他の人に譲ると書かれていたとしても、一定の権利を主張できる制度です。
遺留分の請求に関する時効など詳しい内容は、次の章で解説します。
少しでも遺言に疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
4.遺言無効と遺留分侵害額(減殺)請求を併せて検討すべき理由
遺言書の内容に納得できず「無効にしたい」と考える場合、同時に検討しておくべきなのが「遺留分侵害額請求」です。
これは、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人が、その分に相当する金銭の支払いを請求できる制度です。
この請求は、相続が始まり、かつ遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなければ、時効で消滅してしまうため注意が必要です。
遺言を無効にしたい場合でも、訴訟で無効と認められるとは限りません。
そのため、遺言の無効を主張しつつも、念のため遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことで、いざ無効が認められなかった場合でも、最低限の取り分を請求する道を残すことができます。
なお、請求後に発生する「金銭を支払ってもらう権利」は別のものとみなされ、これについては最長5年で時効になる点にも留意しましょう。
遺言無効に関する不安や疑問がある方は、半田みなと法律事務所に相談を

遺言を無効にできるかどうかは、自分だけで判断するのは簡単ではありません。
遺言書の有効性を争うには、法的な知識や手続きが必要になるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
半田市宮本町にある半田みなと法律事務所では、初回無料相談を行っており、ご家族の不安や疑問に丁寧にお応えします。
大会議室を完備しているため、ご家族全員でのご相談や今後の方針決定の場としてもご利用いただけます。
また、遠方の方にはオンラインでのご相談にも対応可能です。
司法書士・税理士との連携により、相続登記や財産整理など複雑な手続きも一貫してサポートいたします。
遺言や相続に不安を感じたら、お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。