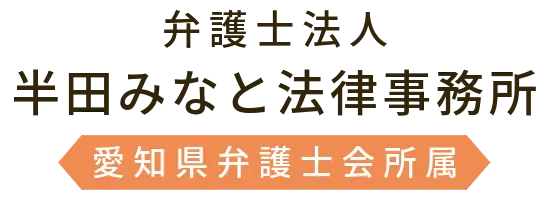亡くなった方が所有していた不動産を相続する場合、相続人が所有権を取得するには相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されましたが、実際にいつまでに何をどう申請すればいいのか、分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記の義務化とはどんなものなのか、義務化された背景、相続登記をしないとどうなるのか、手続き方法や、義務をより簡単に履行できる制度などについて解説します。
相続登記とは?2024年4月から義務化!
そもそも、相続登記とはどんな手続きなのか、相続登記が義務化されてどのような点が変更になったのか、解説していきます。
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から不動産を相続した時に、不動産の名義を相続人に変更することです。相続人はその不動産の所在地を管轄する法務局に「相続を原因とする所有権移転登記」を申請することで、不動産の所有者が誰なのか明らかにすることができます。
正しく相続登記を行うことで、土地や建物の所有権を主張することができ、不動産の売却や不動産を担保にすることなどができるようになるというメリットがあります。将来のトラブルを防ぐために必要な申請ですが、相続登記の手続きは複雑で、相続登記によって不動産を所有していることが登録されるため固定資産税の支払いが生じるといったデメリットもあります。
相続登記の義務化とは?いつまでに申請が必要?
これまでは相続登記の申請は相続人の任意とされ、法的なルールはありませんでした。そのため、相続登記によるデメリットを避けるために手続きを行わない相続人もいることが問題となっていました。
そこで、2024年(令和6年)4月1日から相続登記を義務化する法律が施行され、期限内に相続登記を行わない場合には罰則が設けられました。相続登記の期限は「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。ただし、被相続人が不動産を所有していたことを認知していない期間は、この3年には含まれません。
相続登記の義務化では、過去の相続も対象に
相続登記の義務化のもう一つのポイントは、過去に相続した不動産で相続登記をしていないものについても登記が義務付けられることです。過去に相続した不動産については、2027年3月末までの申請が義務付けられています。正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去の相続分であっても罰則の対象となります。
ちなみに、「正当な理由」として認められるものには、以下のようなケースが挙げられます。
- 相続人の数が極めて多数で、書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性について争いがある場合
- 相続人が重病である場合
- 経済的に困窮している場合
ただし、これらの理由に該当するから義務を免れるということではなく、最終的には法務局の登記官が個別事情を確認して判断します。
相続登記が義務化となった背景
相続登記が義務化された理由の一つに、「所有者不明土地」問題が挙げられます。
相続登記手続きを行わないと、その土地や建物の所有者が特定できないままになります。このような、法務省の登記簿などを調べても所有者が分からない土地や、所有者が分かっていてもすでに亡くなっているなど連絡が取れない土地のことを「所有者不明土地」と言います。
所有者不明土地は、土地の権利者が不明となっているため、適切に活用や処分をすることができません。この土地を公共事業や都市開発などのために有効活用するには、所有者を捜索して、すべての相続人に連絡を取って合意を得る必要があり、多くの費用と時間がかかってしまいます。また、空き地や空き家として長期間に渡って放置された結果、ゴミの不法投棄や不法占有する者が現れるなど、さまざまなトラブルにつながる可能性も考えられます。
所有者不明土地は年々増加傾向にあり、活用できない土地が増えることは経済的な損失となることから、大きな社会問題となっています。この問題の解消実現を目指して、不動産の所有者を明確にするために相続登記が義務化されたのです。
相続登記の義務化の後も対応しないとどうなる?

相続登記をしないと、法律で定められた罰則を受ける可能性や、不動産の所有権が明確でないためにトラブルが起きる可能性が考えられます。一つずつ見ていきましょう。
罰則
正当な理由なく不動産の相続登記を3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。また、不動産の所有者の氏名・住所が変更になった場合には、2年以内に変更手続きをすることが義務となっており、変更手続きがなければ5万円以下の過料が求められることになります。
トラブルに発展するリスク
相続登記をしないと、法による罰則以外にも、不動産の所有権が明確でないためにトラブルになってしまう可能性があります。
相続登記をしないまま放置して長い期間が経つと、相続人も亡くなり、今度は相続人の子(所有者の孫)が相続人となるなど、相続人の数が増えるケースがあります。こうなると権利関係が複雑になり、相続人全員で合意して相続登記をすることが難しい状況になってしまいます。
また、不動産を売却したり担保として提供したりするためには、実際の所有者と登記簿上の所有者が一致していなければなりません。相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままになっているので、売却や担保としての提供ができなくなってしまいます。
さらに、相続人の中に借金がある人がいる場合、不動産を差し押さえられてしまう可能性もあります。不動産を相続していない相続人が権利関係に入ってくるとさらに複雑な状況となってしまいます。
相続登記の手続き方法や注意点、簡単に相続登記義務を履行できる方法
相続登記の手続きは自分で行うこともできますが、法律によって必要書類や申請書の書き方などについて細かく決められているため、正確に申請することは簡単ではありません。期限内に申請できない可能性があることから、相続登記の義務化に合わせて、より簡単に相続登記義務を履行できるように「相続人申告登記の申出」という制度が設けられました。
ここでは、相続登記の手続き方法や自分で手続きする際の注意点、「相続人申告登記の申出」について解説していきます。
手続き方法
大まかな相続登記の流れは以下の通りです。
- 相続する不動産(土地・建物)を確認する
- 遺言または遺産分割協議によって相続人を決定する
- 相続登記の申請書を作成し、必要書類を収集する
- 相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請する
- 手続き完了後、登記事項証明書で変更内容を確認する
必要書類には、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑登録証明書、固定資産課税明細書、遺産分割協議書や遺言書などがあります。申請書や必要書類を揃えたら、管轄の法務局の窓口か郵送で提出します。完了書類を受け取ったら内容を確認し、登記事項証明書を発行して名義が正しく変更されているか確認しましょう。必要書類は遺産分割協議の場合と遺言書がある場合で異なります。
注意点①相続人全員の合意が必要となる
遺産分割協議によって被相続人の財産を分与する場合には、不動産の相続人を決めるために他の相続人も含めた全員に合意を取ることが必要となります。相続人全員の合意があって遺産分割協議書を作成した後に、不動産を相続した人が相続登記をすることができるようになるのです。
相続人の数が少なくお互いに良好な関係であれば、大きなトラブルにはなりにくいと考えられます。しかし、相続人が多く面識もないケースであれば、全員と連絡を取るだけでもかなりの労力と時間が必要となるでしょう。特に、相続人同士で意見の対立があったり、音信不通の相続人がいたりする場合には、期限内に相続登記を行うことが困難となる可能性があります。
注意点②費用がかかる
相続登記には、登録免許税や必要書類の発行手数料といった費用がかかります。自分で手続きをするのが難しい場合には、これらの費用に加えて司法書士や弁護士などの専門家に依頼するための費用も必要となります。
登録免許税とは、登記や登録をする際に課される税金のことで、相続登記の場合は不動産の固定資産税評価額の0.4%と定められています。必要書類となる各種証明書を発行するためにもそれぞれ500円から700円ほどの費用がかかります。
平日に何度も役所に行くことができないなど、自分で手続きをすることが困難な場合には、司法書士に依頼するための報酬が必要となります。相続人の間でトラブルになっている場合やトラブルになる可能性が高い場合には、弁護士に依頼することで紛争の解決や遺産分割協議の調整、その後のサポートまで任せることができます。
期限内に相続登記できない場合は「相続人申告登記の申出」を利用できる
遺産分割協議がなかなかまとまらないなど、期限内に相続登記の義務を履行したくてもできない場合、「相続人申告登記の申出」という制度を利用することができます。これによって暫定的に相続登記の義務が履行したとみなされ、罰則を免れることができるのです。
「相続人申告登記の申出」とは、不動産の所有者(名義人)に相続が発生したことと、自身が相続人であることを法務局に申し出ることです。オンラインでの申し出も可能で、押印や電子署名も必要ないため、通常の相続登記よりも簡単に義務を履行することができます。
ただし、この申し出によって不動産の所有権を取得することはできません。不動産の所有者として自由に使用したり売却したりするためには、正式に相続登記を申請する必要があります。
相続でお困りの場合は弁護士にご相談を

相続登記の義務化によって、不動産を相続してから3年以内に相続登記をすることが求められます。しかし、実際には遺産分割協議が長引くなど、期限内に申請することができないケースもあります。また、相続登記の申請には細かいルールや必要書類が多く、自分で行うのは簡単ではありません。
遺産分割協議や相続登記でお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続をめぐる紛争の解決までサポートすることが可能です。煩雑な相続登記の手続きもスムーズに進めることができます。
半田みなと法律事務所は、半田市を中心に知多半島全域で相続問題についてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。弁護士とファイナンシャルプランナーが連携し、相続に関する法律や税務など、トータルサポートをご提供しております。少しでもお力になれればという思いで、初回30~60分の無料法律相談を実施しており、弁護士費用も比較的低価格でご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。