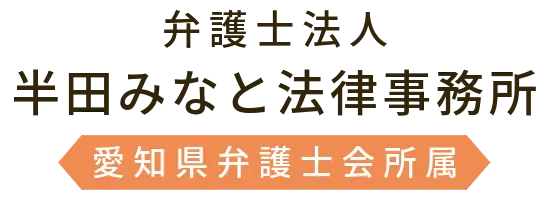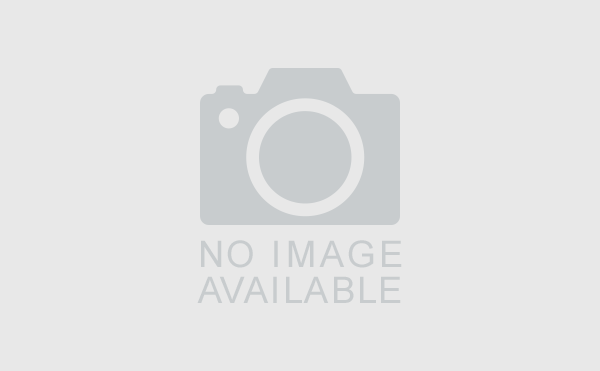不動産は遺産の中でも価値が高いものとなるケースが多いものの、相続人同士で分けることが難しい財産のため、相続においてトラブルになりやすい傾向があります。兄弟仲がいいから大きな揉め事にはならないだろうと思っていても、実際に遺産相続の段階になると、お互い一歩も譲らず争いに発展することもあるのです。
相続人間でトラブルになってしまった場合には、当人同士で話し合いをするだけでなく、弁護士などの専門家を交えて冷静に解決を図るのも非常に効果的です。
今回は、不動産相続でトラブルが起きやすいポイントや、不動産の遺産分割方法などについて解説します。
不動産相続でトラブルになりやすいポイント6選
不動産相続では、以下のようなポイントがトラブルになりやすい傾向があります。
- 不動産を誰が相続するか
- 不動産の分割方法
- 不動産の評価額や評価方法
- 不動産相続にかかる税金
- 不動産の名義に問題があった
- 相続不動産の管理
1つずつ見ていきましょう。
誰が不動産を相続するか
不動産の評価額が高い場合や、相続財産が不動産しかない場合などには、不動産を相続したい人が複数いてトラブルとなるケースがあります。例えば親が亡くなり、子である兄弟が全員不動産の取得を主張した場合、誰かが譲らない限り遺産分割協議がまとまらず、相続手続きを進めることができません。
また、不動産の資産価値が低い場合や、不動産が相続人の居住地から遠方にある場合などには、取得したい相続人がおらず、誰が引き取るかで揉めることもあります。亡くなった親が田舎に住んでおり、自宅として使っていた不動産があるものの、子は都会で生活しており、活用も売却も難しいといったケースで考えてみましょう。不動産を取得した相続人には、固定資産税や建物の維持費用といった負担が発生するため、誰も取得したがらないという事態になってしまう可能性があります。不動産の取得人が決まらないと、不動産以外の現金を含めた遺産分割を進められません。
不動産の分割方法をどうするか
不動産そのものを分割することは難しいため、遺産分割協議が難航した場合に「とりあえず相続人全員の共有名義にする」という方法が取られることがあります。しかし、これが後になってトラブルとなるケースも多いです。
不動産を共有名義にすると、名義人のうち1人でも反対する人がいると、売却や賃貸ができません。また、被相続人(亡くなった方)の生前からその不動産に住んでいた相続人が、共有名義となった後も単独で住み続け、家賃をめぐって他の名義人とトラブルになることも。さらに、固定資産税や維持費を誰が負担するのかという問題や、相続人たちの子ども(被相続人の孫)の世代では相続人が増えるため、遺産分割がさらに難しくなってしまう問題も考えられます。
不動産の遺産分割の方法は4つあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。この記事の後半で解説していきます。
不動産の評価額や評価方法
公平な遺産分割のためには、不動産の評価額を査定してもらう必要があります。しかし、不動産を評価するには複数の方法があり、どの方法を採用するかで評価額が異なるため、どの評価方法で資産価値を計算するかでトラブルになるケースも多くあります。
遺産分割で採用されることが多い不動産の評価方法には、以下の2つがあります。
- 路線価方式…道路に面する土地の1㎡あたりの価格(路線価)を基に評価する方式。相続税課税額を算出する際に適用される。
- 時価…似た取引条件の不動産が実際に売買された取引価格のこと。不動産がいくらで売れそうかを検討する際に採用される。
不動産相続にかかる税金
資産価値が高い不動産は、相続税や譲渡所得税といった税金も高額になります。不動産を相続で取得したものの、相続税が高額で払えないケースも発生しやすいでしょう。また、遺産の不動産を売却して相続人同士で利益を分配することにしたものの、譲渡所得税を誰が支払うかで揉めるといったトラブルも起きやすい傾向があります。
不動産の名義に問題があった
相続した不動産の名義が被相続人の親など、ずいぶん前の代のままになっているケースでは、登記が行われていない分の相続登記(相続した不動産の名義変更)をしなければ名義を変更できません。しかし、相続登記にはさまざまな証明書が必要となるため、前の代の相続から長い時間が経っていると必要な書類を揃えることができないこともあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化となりました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしない場合、原則として10万円以下の過料が課されます。これは2024年4月よりも前の相続分であっても例外ではなく、2027年3月末までに相続登記を申請する必要があります。
しかし、長期間に渡って名義変更が行われていなかった不動産の相続登記は簡単ではありません。過去にどのような相続が行われ、誰が所有者だったのかを調査し、各所にあたって必要書類を集め、適切に申請する必要があり、膨大な労力と時間を要します。自分だけでは抱えきれない場合には、専門家である弁護士に依頼しましょう。
さらに詳しくは、「相続登記の義務化とは?期限や罰則、簡単に履行できる新設制度も解説」のコラムもご覧ください。
相続不動産の管理
相続した不動産が遠方にあるなど、頻繁に訪問管理をするのが難しいケースも多いです。住む人がいなくなった住宅は劣化が早いため、空き家となり倒壊のリスクを抱えるなど、近隣の迷惑となる可能性があります。
また、遺産分割協議が終わっておらず誰が不動産を相続するか決まっていない段階にも関わらず、相続人の1人が勝手に住み始めてしまうケースもあります。
不動産の遺産分割の方法は4種類!

不動産を相続する際の遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあります。遺産分割協議は相続人全員が納得して合意する必要があるため、遺産分割の方法は相続人同士で話し合って決められます。4つの分割方法のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
現物分割
不動産を相続人の1人または複数人がそのままの形で相続する方法です。面積100㎡の土地であれば、1人がすべての土地を相続したり、50㎡の土地に分けて2人で相続したりすることができます。
現物分割のメリットは、相続人が自由に不動産を活用したり売却したりすることが可能となることです。被相続人の生前からその不動産に一緒に住んでいた相続人が、そのまま住み続けることができます。また、相続登記が比較的簡単に申請できるのもメリットと言えます。ただし、複数の相続人で土地を分ける場合、細分化されて活用しにくくなるというデメリットがあります。
代償分割
代償分割は、1人の相続人が不動産を現物で取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことで、不動産と他の相続財産との資産価値の差を埋めて公平に相続する方法です。
メリットは、不動産を取得したい相続人がそのままの状態で相続することができ、他の相続人とも公平な遺産分割ができるという点です。さらに、代償金を支払うことで、相続税の支払額を減らすことができる可能性もあります。
デメリットとしては、相続人に十分な資産がない場合には代償金を支払えずトラブルになることもある点や、代償金の金額を決める際に他の相続人と揉める可能性がある点などが挙げられます。
換価分割
換価(かんか)分割は、相続する不動産を売却した利益を分配する方法です。金銭となるので複数の相続人がいても平等に分けることができ、今後の不動産の管理や税の支払いをめぐるトラブルを防ぐことができます。
ただし、売却のために買い手を見つける必要があり、手続きが複雑になるため税理士など専門家に依頼するための費用が発生するといったデメリットもあります。また、売却して得た利益には所得税や住民税が課税されるため、実際に分配される金額は売却価格よりも低くなってしまいます。
共有分割
共有分割は、複数の相続人が共有状態で相続する方法です。相続分割協議がなかなか進まない場合、共有分割をすることで公平な遺産分割が行えるため、協議がまとまりやすくなる傾向があります。
デメリットは、後でさまざまなトラブルになりやすいことです。共有分割にした不動産を売却や増改築する場合には、相続人全員の合意が必要となるため、管理が複雑になります。また、共有分割にした不動産をそのままにしておくと、被相続人の孫世代になった時に共有者が分かりにくく、手続きが煩雑になってしまうことも。共有分割をおすすめできるケースとしては、近い将来にその不動産を売却することが決定している場合などが挙げられます。
不動産相続トラブルを弁護士に相談すべき理由
不動産は資産価値が高く、トラブルになりやすいポイントも多いため、相続人同士の話し合いで遺産分割協議を完結させることは簡単ではありません。仲のいい兄弟でも、相続をめぐって争いが長期化することも珍しくはないのです。トラブルなくスムーズに遺産分割協議を進めるには、なるべく早い段階から弁護士に依頼して間に入ってもらうことが重要です。
弁護士は、相続人同士で起きたトラブルへの対応や、被相続人に借金がある場合の相続放棄手続き対応など、相続に関する幅広いサポートが可能です。相続財産調査や相続人調査も行うことができ、司法書士や税理士など他の専門家と連携して、相続税を減らしたり不動産の相続手続きをスムーズに完了させることもできます。
また、被相続人が存命であれば、遺言書の作成や生前贈与の段階から弁護士のサポートを受けるのも非常に効果的です。法的に効力のある遺言書を作成することで、遺産分割協議書を作成する必要がなくなるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
半田みなと法律事務所は、半田市を中心に知多半島全域で相続問題についてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。例えば、「相手方に不動産の適切な金額を主張して1800万円を取得した事例」などもございます。弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーが連携し、相続に関する法律や税務など、トータルサポートをご提供しております。初回30~60分の無料法律相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。