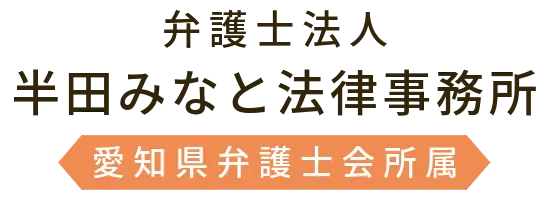被相続人(亡くなった方)の財産を調べていると、借金や債務といったマイナスの財産が多く発見された、というケースも多くあります。財産を相続した場合、借金の返済義務も相続することになってしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合には相続放棄という選択肢も検討しましょう。
相続放棄には期限があり、申請にあたって準備しておくべきことも多いため、事前に知識を付けて対応できるようにしておくことが大切です。この記事では、相続の種類を簡単にご紹介し、相続放棄の手続きの流れや、相続放棄をしても受け取れる財産、注意点などについて詳しく解説します。
相続放棄とは?相続の3つの種類
被相続人が亡くなり、相続が開始した際には、相続人は以下の3つの相続方法から選択することができます。
- 相続放棄
- 単純承認
- 限定承認
相続放棄や限定承認を選択する場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨の申述をする必要があります。期限内に申述がなければ、原則として単純承認をすることとなります。
それぞれの相続方法についてご紹介していきます。
相続放棄
相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続方法です。預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産も、借金や各種ローン、滞納している税金や家賃などのマイナスの財産も、すべて引き継がずに放棄します。相続放棄が認められたら、相続人は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合や、被相続人に連帯保証債務がある場合などには、相続放棄が選択されることがあります。また、相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄が良い選択となるケースもあります。
ただし、マイナスの財産が多い場合に相続放棄をすると、その分だけ他の相続人にマイナスの財産を負担させることになるため、相続人同士で相談して決めることをおすすめします。
単純承認
被相続人のすべての権利や義務を引き継ぐのが単純承認です。預貯金や不動産の所有権などの権利や、借金やローンといった義務を受け継ぐ、一般的な相続方法です。
どの財産を誰が引き継ぐのかは、被相続人の遺言書があればその記述の通りに分配します。遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない財産が後から出てきた場合などには、相続人同士で遺産分割協議を行います。
限定承認
限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産を限度に、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産とマイナスの財産の両方があると分かっているものの、被相続人の債務がどれくらい残っているのか不明という場合、債務が少なければ受け取れる財産が残る可能性があります。そのようなケースでは限定承認が選択されることがあります。また、遺産にマイナスの財産が多いものの、思い入れのある実家など放棄したくない財産もあるというケースでも利用されます。
後になって被相続人の債務が見つかった場合、単純承認の場合はその債務も相続することになってしまいます。限定承認なら、引き継ぐべき債務は遺産相続によって得た財産が限度となるため、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多くなることはありません。
限定承認も、相続放棄と同じく家庭裁判所に申述しなければいけません。相続放棄は相続人のうち1人でも申述できるのに対して、限定承認の場合は相続人の全員が共同で申述する必要があります。
相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をする際に必要な申述について、手続きの流れを解説していきます。
1. 遺言書があるかどうか確認する
まずは、被相続人の遺言書があるかどうか、その内容は納得のできるものかを確認しましょう。
法的に有効な遺言書があれば、その内容の通りに相続人間で財産を分割します。マイナスの財産を自分が引き継ぐことになるとは限りません。遺言書がある場合でも、相続人の全員の同意があれば遺産分割協議を行い、相続人同士の話し合いで遺産を分割することができます。
2. 相続財産を調べて放棄すべきか検討する
マイナスの財産があり相続放棄を検討する場合には、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて調べて把握します。借金がある場合は具体的に何円なのか、未払いの税金の内訳と金額、保証債務はどのくらいあるのかなど、漏れなく調べましょう。
調べる手段としては、被相続人のエンディングノートや、生前に住んでいた家に保管された契約書や督促状などの書類などが挙げられます。価格が明確でない不動産や美術品などについては、評価額を適切に判断しましょう。
3. 必要書類を用意する
相続放棄の手続きに必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 住民票除票または戸籍附票
- 申述する方の戸籍謄本
「相続放棄申述書」には、被相続人や申述する方の住所や氏名、相続放棄する理由、相続財産の内容などを記載して作成します。裁判所のホームページでダウンロードすることができ、記入例も示されています。記入を終えたら、収入印紙と必要書類、連絡用の郵便切手などを添えて、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。窓口に直接持参しても郵送でも提出することができます。
4. 「照会書」や「相続放棄申述受理通知書」が届く
必要書類を提出すると、家庭裁判所から質問がある場合には「照会書」が送られてくる場合があります。回答したり追加書類を用意したりして、返送しましょう。
「相続放棄申述受理通知書」が届くと、申述の手続きは完了です。
5. 借金がある場合は「相続放棄申述受理証明書」を申請する
被相続人が借金をしていた場合、債権者から返済を求められる場合もあります。そのような場合に備えて、裁判所に別途申請して「相続放棄申述受理証明書」を取得し、保存しておきましょう。この証明書によって、相続放棄をしたことを客観的に明らかにすることができます。
相続放棄の注意点
相続放棄は、メリットだけでなくデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。相続放棄に関する注意点を4つご紹介します。
相続放棄には期限がある
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄申述書を提出する必要があります。書類の提出前に相続財産をすべて調査し、各所を回って必要書類を集めなければならないので、相続放棄するかどうか短期間で判断することになります。
ただし、相続財産を調べたものの、複雑で調査に時間がかかってしまう場合や、他の相続人と連絡が取れない場合などには、期間を延長してもらうように家庭裁判所に申し立てることも可能です。
相続放棄をしたら撤回や代襲相続ができない
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が、相続開始前に死亡したり相続権を失ったりした場合、本来の相続人の子や孫が代わりに相続することです。しかし、相続放棄をしたら初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続ができません。
また、相続放棄は原則として撤回できないため、後からプラスの財産が大量に見つかってマイナス財産よりも多いことが発覚したとしても、取得することはできません。
相続放棄をしても受け取れる財産がある
相続放棄を選択した場合でも、以下のような相続財産に該当しないものであれば、受け取ることができます。
- 被相続人の死亡保険金(受取人に指定されていた場合)
- 香典、ご霊前
- 仏壇、お墓(祭祀財産)
- 葬祭費、埋葬料
- 死亡退職金(受取人に指定されていた場合)
- 遺族年金、未支給年金
相続放棄ができないケースもある
単純承認として相続したと認められる場合には、相続放棄ができないケースもあります。例えば、以下のような行為には注意が必要です。
- 遺品整理として財産を処分した
- 被相続人の預貯金を解約した
- 生前住んでいたアパートの契約を解除した
- 被相続人が滞納していた家賃を支払った
- 生前の入院費や介護費用の支払いを、被相続人の預金口座から行った
このように、相続財産を処分・消費・隠匿した場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄を検討している場合は、手続きが完了するまでは被相続人の財産に触らないようにすることが大切です。
また、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後にマイナスの遺産が発覚した場合でも、相続放棄ができない可能性もあります。
相続放棄をご検討の際は弁護士のサポートを受けるのがおすすめ

相続放棄を検討する際には、すべての相続財産を漏れなく調査することが重要なポイントです。後からマイナスの財産が出てきても、プラスの財産が出てきても、相続方法を変更することは非常に難しいのです。
とはいえ、被相続人が残したすべての相続財産を漏れなく調査するのは簡単ではありません。思いも寄らないところから、相続財産が出てくることもあります。弁護士に依頼すると費用はかかるものの、法律の専門知識と弁護士に与えられた権限を利用して、スムーズに、そして正確に相続財産を調査することが可能となります。弁護士照会という権限を使うことで、金融機関や公的機関に情報開示を請求することができ、個人で調査するよりも効率的に進めることができます。また、相続に関する複雑な手続きも全般的に任せることができ、相続人同士のトラブルにも対応してもらうことができるため、心理的なストレスや手間を大きく軽減させることも可能です。
半田みなと法律事務所は、半田市を中心に知多半島全域で相続問題についてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。弁護士だけでなく、税理士と司法書士とも連携しており、相続に関する法律や税務など、トータルサポートをご提供しております。少しでもお力になれればという思いで、初回30~60分の無料法律相談を実施しており、弁護士費用も比較的低価格でご利用いただけます。マイナスの相続財産によって不要な負担を引き継がないようにするためにも、ぜひお気軽にご相談ください。